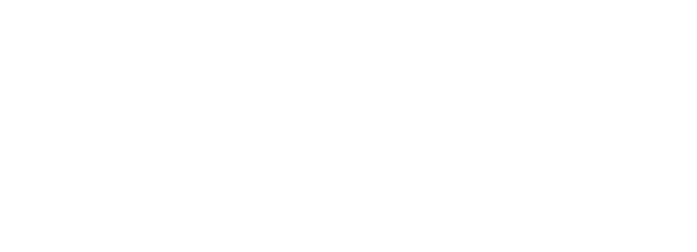
お電話・メールでの
お問い合わせはこちらから
当事務所では,刑事弁護の実務に関するテーマを決めて,当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに,
参加者全員でその理解を深める「刑事実務検討会」を当事務所にて定期的に開催しています。
今回のテーマは「公判に向けた計画的な準備」です。
次回の刑事実務検討会は、2月10日(木)18時30分から、徳永裕文先生と戸塚史也先生に講師を
務めていただき、公判に向けた計画的な準備について研修を行います。
公判は、1回限りのものであり、そこでした一挙手一投足が事件の命運につながるといっても過言ではありません。
また、公判では、往々にして予想外のことが発生し、瞬時の判断が求められます。このような公判で十分な力を
発揮するためには、十分な準備をすることが不可欠です。しかし、準備する時間には限りがあります。
そこで、今回の実務検では、限りある時間のなかで、公判に向けていかに計画性を持って準備をするのか、
ということに焦点を当ててお話をしたいと思います。
弁護士(若手のみでなく中堅以上の先生方もぜひご参加ください)・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。
参加を希望される方は,準備の都合上,事前にご連絡ください。
なお,今回の刑事実務検討会は,Zoomを利用して行います。参加をご希望の方は,事前にURLをお送りいたします。
開催日:2022年2月10日(木)18時30分~
テーマ:公判に向けた計画的な準備
講師:徳永裕文先生、戸塚史也先生
参加お申し込み先メールアドレス:kitapubinfo(at)kp-law.jp
※お手数ですが,送信の際は(at)の部分を@に置き換えてお送りください。
2022年2月1日 4:39 PM カテゴリー: 研究会等のご案内
建造物侵入及び窃盗被疑事件で、処分保留により被疑者が釈放される成果を獲得しました。
(担当弁護士:國府田豊)
2022年1月27日 2:05 PM カテゴリー: 事例報告
現住建造物等放火未遂被疑事件で、不起訴処分となり被疑者が釈放される成果を獲得しました。
(担当弁護士:徳永裕文、國府田豊)
2022年1月27日 2:03 PM カテゴリー: 事例報告