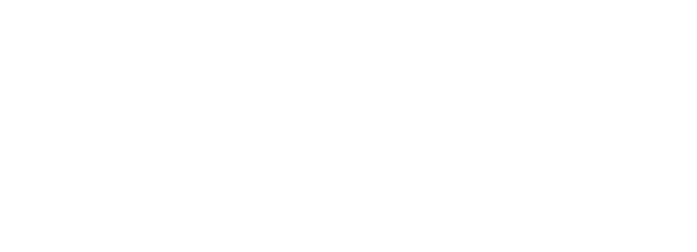
お電話・メールでの
お問い合わせはこちらから
白井徹弁護士、山田恵太弁護士、牧田史弁護士、須﨑友里弁護士、桑原慶弁護士の5名が昨年12月末で退所いたしましたのでお知らせします。
白井弁護士は法律事務所ヒロナカ、山田弁護士と牧田弁護士はアリエ法律事務所、須﨑弁護士は高野隆法律事務所、桑原弁護士は法テラス島根法律事務所へそれぞれ移籍しました。
2017年1月5日 11:44 AM カテゴリー: 弁護士入退所のお知らせ
当事務所は,今回,地方赴任希望者のみを対象とする第70期司法修習生の採用選考を行うことになりました。
今回の募集は,ひまわり基金法律事務所への赴任等,地方へ赴任するために当事務所で一定期間(概ね2,3年程度)の養成を受けることを希望する者であることが条件となります。
以下,その募集要項です。
【募集要項】
1 募集人数
1名程度
2 選考方法
書類審査の上,書類審査を通過した方に面接審査を実施いたします。
3 応募方法
以下の応募書類を応募期間内に当事務所宛に郵送にてご提出下さい。
[応募書類]
①履歴書(市販のもので可。写真貼付のこと)
・ 現住所,実務修習地,並びに,ご連絡先として,必ず連絡の取れるメールアドレス及び電話番号を明記してください。
・ 書類選考の合否等,今後のご案内はメールにて行います。そのため,メールアドレスは,お間違えのないようにご記載ください。ハイフン,アンダーバー,大文字,小文字等,間違えやすい文字,記号は特に注意してご記載ください。メールアドレスに誤記や判読不能文字があった場合,ご連絡できないまま手続を進めざるをえなくなることがありますので,ご承知おきください。
②応募理由書(1000字程度)
③成績証明書(最終学歴のもの)
④司法試験成績通知書の写し(合格した年の短答・論文試験のもの)
⑤任意提出書類
・ ひまわり基金法律事務所への訪問またはひまわり基金法律事務所への赴任経験者へのインタビューをした報告書等
・ TOEIC,法律関連資格等,弁護士業務との関係で自己PRになるものがあれば,写しをご同封下さい。なお,任意提出書類に該当するか否かの問い合わせには応じられませんので,ご自身で判断して下さい。
4 応募期間
2017年1月20日(金)~2017年1月27日(金)(必着)
5 面接要領
(日時)2017年2月12日(日) 午後1時より,順次実施
(場所)当事務所
・ 書類審査を通過した方に,上記面接日時に面接を1回受けていただきます。面接を受けていただく方には,2月1日(水)頃に,メールにて,面接の時間をご通知いたします。
・ 面接の時間は当方で指定させていただきますが,遠隔地に住んでいる等の特段の理由により時間帯に制約のある方は,応募書類郵送時に書面にて申し出てください。可能な範囲で配慮いたします。
【事務所概要】
当事務所は,刑事対応型都市型公設事務所です。
刑事弁護のプロフェッショナルとして,死刑求刑事件など重大な刑事事件の弁護を担うほか,地域に根ざした法律事務所として,区,地域包括支援センター,権利擁護センターなど行政との連携を深め,高齢者・障がい者などの社会的弱者の人権擁護活動にも積極的に取り組んでおります。
また,過疎地における弁護士需要に応えるべく,当事務所で養成を受けた数多くの弁護士がひまわり基金法律事務所や法テラス各地方事務所に派遣されています。
法曹養成のため,エクスターンシップ(一橋,慶應,早稲田,上智,青山学院)の受け入れ等を行っております(平成27年度実績)。
上記の各分野に関心があり,市民のための弁護士として,どんな事件でも厭うことなく引き受ける意欲のある方を求めます。
〒120-0034
東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスⅡ番館
TEL03-5284-2101 FAX03-5284-2104
ホームページ; http://www.kp-law.jp/
弁護士法人北千住パブリック法律事務所
代表弁護士 大 谷 恭 子
2016年12月22日 3:41 PM カテゴリー: 採用情報
12月12日、若草プロジェクト代表理事の大谷恭子弁護士が、吹田市立男女共同参画センター デュオの平成28年度意識啓発講座 Wリボンプロジェクトinすいた2016エンディング「つなぐ人、まち、すいた~暴力のない社会をめざして~」において、生き難さを抱えた若い女性たちをテーマに、若草プロジェクトの活動などについてお話ししました。
2016年12月19日 2:29 PM カテゴリー: 講演、執筆等
12月9日、大谷恭子弁護士が、福岡県小中学校養護教員研究会の冬期研修会で、「障害者差別解消法について~教育現場における合理的配慮~」と題した講演を行いました。
2016年12月19日 2:28 PM カテゴリー: 講演、執筆等
12月8日、大谷恭子弁護士が、2016年度部落解放・人権大学講座で、「障害者の人権―障害者権利条約批准と障害者差別解消法の制定―」についての講師を務めました。
2016年12月19日 2:28 PM カテゴリー: 講演、執筆等
大谷恭子弁護士が、11月9日、立正佼成会「平成28年次職員人権啓発講座」、並びに、11月25日、真言宗豊山派「宗立全国同和推進・人権擁護講習会」で、“分け隔てなく、あなたらしく、地域で生きる”をテーマに、障害者差別解消法や合理的配慮についてお話ししました。
2016年12月19日 2:27 PM カテゴリー: 講演、執筆等