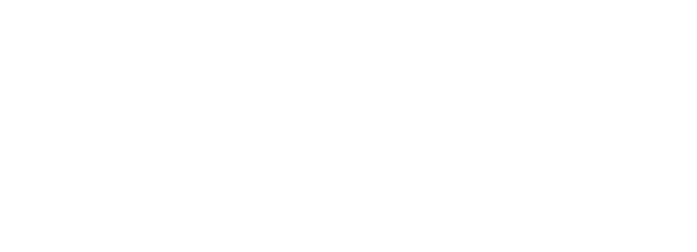【配偶者居住権と跡継ぎ遺贈型受益者連続信託】(弁護士 國井敏明)
平成30年に相続法が改正され、新たに配偶者居住権の制度がつくられました。
令和2年4月1日から施行される民法1028条1項には、次のように定められています。
「被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この説において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。」
配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判に別段の定めがなければ、配偶者の終身の間とされています(民法1030条)。
また、配偶者居住権の設定の登記を備えることができ、登記を備えた場合は第三者に対抗できます(民法1031条)。
配偶者居住権の制度によって、例えば遺産分割の際、配偶者が低廉な価額で居住権を確保できるといわれています。つまり、遺産分割の際、遺産の1つである建物に引き続き居住するためその所有権を取得するとなると、自己の法定相続分を超える建物の価額について、他の共同相続人に代償金を支払う必要が生じるかもしれないからです。
とはいえ、例えば父親が亡くなり、母親と実子との間で遺産分割をする場合であれば、代償金なしに母親に不動産を相続させ、母親の取り分が法定相続分より多くなったとしても、誰も文句を言わないかもしれません。不動産は、2回の相続を経て子の世代に承継されますが、夫婦の間で財産を相続したときの相続税は配偶者の税額軽減制度をつかえ、小規模宅地の特例もつかえるかもしれないので、相続税の点でも不利益のないケースが多そうです。
そうだとすると、配偶者居住権が活躍する場面はそれほど多くなさそうでしょうか?
典型的な活躍の場面として考えられるのは、実子のいる高齢者が再婚した場合です。
例えば、父親が再婚したケースで、父親が亡くなった後、再婚相手に父親の不動産を相続させると、再婚相手が亡くなった後は再婚相手の相続人のものになってしまいます。しかし、例えば先祖伝来の不動産を、赤の他人の手に渡すわけにはいかないかもしれません。
このような場合は、配偶者居住権の制度を活用し、再婚相手は配偶者居住権を取得し、所有権は実子が取得するのがいいかもしれません。
ところで、配偶者居住権の制度ができる前は、実子がいて再婚した高齢者の相続のケースを、あらかじめうまく解決しておく方法はなかったのでしょうか?
これについては、「跡継ぎ遺贈型受益者連続信託」を利用することで、従前から類似の法律効果を得ることができました。
「信託」とは、信託契約の締結などの信託行為によって、受託者が信託財産について財産権の移転を受けた上で信託目的に従って信託財産の管理・処分などを行い、その管理・処分にともなう利益について受益者に債権的な請求権を取得させる制度です。
そして、「跡継ぎ遺贈型受益者連続信託」を利用し、次のようなことができます。例えば、実子のいる高齢者が再婚した場合なら、まず、不動産を所有する高齢者自身が、当該不動産を信託財産とする信託の委託者 兼 第1次受益者となり、同人の死亡を終期とする受益権を取得します。受益権の内容は、信託不動産を生活の本拠として使用する権利です。次に、第1次受益者が死亡した時点で、再婚相手を第二次受益者として、第2次受益者の死亡を終期とする受益権を発生させます。そして、再婚相手が死亡した時点で、実子を第三次受益者とするか、信託を終了させて実子を信託財産の権利帰属者とします。これらを、信託契約にあらかじめ定めておきます。
このようにすれば、先祖伝来の不動産は、所有者の死後、再婚相手が亡くなるまでは再婚相手が使用する権利を持ちますが、再婚相手が亡くなった後は実子に権利が戻ります。
それでは、類似の法律効果が得られると考えられる、遺言によって配偶者居住権を遺贈することと、跡継ぎ遺贈型受益者連続信託は、どのような違いがあるでしょうか?
やはり、大きな違いは、信託は、「受託者」が登場しなければいけないことでしょう。信託は、信託財産の所有権が、受託者に移転します。ただし、受託者は、信託の利益を享受することが禁止されています(受託者が、受益者を兼ねることはできます。)。受託者は、ただ受益者のために、信託財産の管理・処分などを行うのです。民事信託では、信頼できる親族等に、報酬なしに受託者になってもらうことが多いようです。ちなみに、業として信託の引受けを行うには免許又は登録を必要とするため(信託業法3条、7条)、弁護士が受託者になるのは難しいとされています。
受託者が信託財産を管理することにともなって生じる違いのほか、税金がどうなるかも大きな問題です。信託を利用するのが適したケースは多くないかもしれません。しかし、信託が適したケースももちろんあるでしょうから、現在、民事信託の利用が非常に増えていることも考えると、検討する必要のある選択肢の1つといえるかもしれません。
(なお、信託は、財産の管理と承継のための制度といえます。以上のとおり、配偶者居住権を遺贈する遺言に代えて、財産の承継のため利用できるだけでなく、財産管理の制度でもあることから、成年後見制度に代えて利用することも検討できます。その際、信託財産の管理・処分を受託者によって柔軟に行うことができ、裁判所の関与がほとんどないこと等が、信託の長所といわれています。)
信託の相談は北千住パブリック法律事務所まで。
2019年11月14日 9:29 AM カテゴリー: コラム