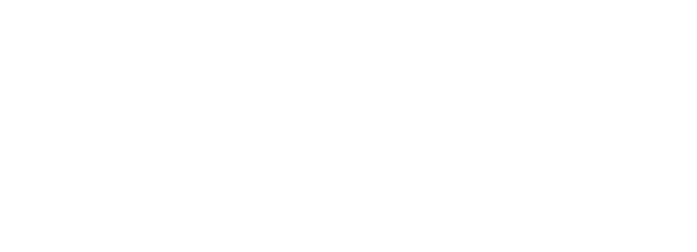
お電話・メールでの
お問い合わせはこちらから
もともと社会系の科目が好きで、法学部なら進路の選択肢も広いだろうと考えて選びました。実際に勉強を始めてみると、特に刑法に惹かれました。刑法は、単に「これは悪いこと」と断じるのではなく、「なぜ悪いのか」「どうして処罰すべきか」といったことを理論的に検討しようとする点が、とても魅力的だと思ったんです。
早稲田大学の法学部に進学し、刑法のゼミに入りました。ゼミの先生の曽根威彦先生は、刑法の謙抑性を重視される先生でした。そうした考えに身近で触れたことも、自分の考え方の根っこに大きな影響を与えていると思います。
刑事事件にかかわる仕事をしたいと思いました。ただ、その選択肢はとても限られていて、法曹か警察官くらいしかありませんでした。私は体力にも自信がなかったですし、いかにも体育会系というイメージがあった警察官は自分に合わないと感じて、ロースクール進学を決めました。
当初は、刑事事件を専門的に扱えるという点で、検察官にも惹かれていました。ですが、ロースクール在学中に北千住パブリック法律事務所(以下、北パブ)でエクスターンを経験して、弁護士の仕事の魅力に気づきました。

もともと、大学やロースクールの犯罪学や刑事政策などの授業のなかで、障害のある方が何度も刑務所に行ってしまう現実に触れ、「これは問題だ」と問題意識を持っていました。
検察官という立場で起訴猶予などを活用するという方法もありますが、どうしても検察官は処罰すべきものに対して処罰を求めるということが仕事の基本姿勢になると思います。しかし、犯罪をした人を単に処罰すればすべての問題が解決するわけではありません。犯罪の背景にある事情に対して、一緒に対策や解決方法を考えて、犯罪をしなくても幸せな生活ができるようになる手助けをすることは、弁護士の立場が一番適切です。そのため、検察官ではなく弁護士として関わるほうが、自分の問題意識に沿うと感じました。
北パブのことを知ったのはロースクールのエクスターンがきっかけでしたが、障害のある方の刑事弁護の分野で活躍されている山田恵太先生の講義を聴いたり、刑事弁護の経験が非常に豊富な山本彰宏先生から法廷弁護技術の指導をいただいたり、ロースクール生のときから、普通の新人弁護士をはるかに上回るような刑事弁護のスキルを学ぶことができました。
エクスターンの後も、学生でも参加できる勉強会である刑事実務検討会に何度も参加していたので、事務所の雰囲気がよく分かりました。懇親会で北パブの先生方と話をする中で、どの先生も活き活きと刑事弁護の仕事をしている様子に魅力を感じ、「こんなふうに働ける弁護士になりたい」と思うようになり、自然と志望するようになりました。
刑事弁護に熱意を持っているのはもちろんですが、1年目から北パブに入って感じることは、若手が多くて、すごく活き活きしている事務所だと思います。特に1年目のときは分からないことや悩むことも多いですが、それらを気軽に相談できる雰囲気があるのがありがたいですね。特に、同期がいることはとてもありがたくて、お互いに愚痴や悩みを相談したり助けてもらったりしたからこそ大変なときでも乗り越えられたと思っています。また、同期や近い期の弁護士が頑張っていたり成果を出したりしている姿を見ると刺激を受けますし、事務所内でも様々な質問が飛び交っていて、皆で学び合っている感覚があります。
頼りがいのある先輩がいることもありがたいです。北パブでは半年間先輩弁護士が指導担当として共同で事件を担当するのですが、半年を過ぎて一人で事件を担当するようになって大変になっていた頃に、その様子を見てくれていた酒田先生がご飯に連れて行って「いつまでも指導担当ですから」と言ってくださったことがあって、とてもほっとしました。
お互いに支え合い、刺激し合いながら成長していける事務所だなと思っています。
弁護士の使命は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」とされています。そして、人権の基本となるのは、幸福追求権、言い換えれば、どんな立場の人であっても、幸せな人生を送ろうとする権利があるということです。つまり、弁護士の仕事は、依頼者が幸せに生活する権利を最大限守ることにあると思います。
刑事事件の依頼者は、こうした幸せな生活がまさに脅かされている状況にあります。冤罪は言うまでもありませんが、たとえ有罪だったとしても不当に重い刑罰を受けるということも、その人に保障されるべき幸せを大きく損なうものです。弁護士として、否認事件であれば無罪を勝ち取ること、量刑事件であれば適切な処分となるよう全力を尽くすことが必要だと思います。
量刑事件では、どんな依頼者でも、丁寧に話を聞いて、どうしてこうなったのかを一緒に考えるよう心がけています。障害や生活の困難など、背景にある課題に向き合うことで、単に罰を科すための「儀式」のような手続にとどめるのではなく、その人が幸せな人生を送ることを支えることにつながるのではと思っています。
初めて一人で受任した刑事事件が、精神的な障害を抱えた方の窃盗事件でした。簡易鑑定の結果、責任能力がないと判断されて不起訴になり、措置入院となりました。不起訴になったことで刑事事件としては終了し、これで弁護士としての仕事は終わったかなと思っていたところ、入院したその日に措置入院先から電話がありました。
「今、手足をベッドにくくりつけられて縛られている」。思いもよらないことを言われて、びっくりしました。電話で医師と話すと、医師は「刑事事件を起こした人で、不穏な状況だったため」と説明しました。確かに、精神保健福祉法とそれを受けた厚労省告示では、身体的拘束の対象となる場合として、「多動又は不穏が顕著である場合」を挙げています。でも、それは自殺や重大な自傷行為を防止するために他の手段がないような場合でなければないんです。この方は、まったく自傷行為をするような人ではなく、留置場でも保護室に入れられたり拘束されたりするようなことはありませんでした。医師に対してこうした反論をしたところ、医師は「先ほど先生と本人が話している様子を見ると、今は落ち着いているようなので、拘束を解除します」と言われました。「留置場では縛られるなんてことはなかったのに、病院に入院したらこんな風に縛られるなんて、留置場の方がよっぽどマシだ」と依頼者から言われ、本当にそのとおりだと思いましたし、病院内が留置場よりも人権が守られない状況にあることに愕然としました。その後、退院請求の代理人という形でその方の代理人につき、3か月後に無事退院できました。一方、退院後は家賃の滞納で建物明渡請求訴訟を起こされ、訴訟に対応しつつ、地域の支援者と一緒に転居をどうするかなど議論しました。
なんとか一段落してから約1年後に、親族の方からの電話でその方が亡くなられたことを知りました。自分ははたしてこの方の幸せに貢献することができただろうかと考えさせられましたし、依頼者の人生を考えたときには、刑事事件が不起訴になったというだけでは決して終わりではないのだということを実感しました。
はい。ちょうど2021年に岡山で開かれる日弁連の人権大会で、精神障害のある人の強制入院の廃止を求める決議がされることになり、そのシンポジウム運営のバックアップ委員になるきっかけにもなりました。その後、日弁連の中に新設された強制入院廃止の実現本部にも加わることになり、現在も活動しています。
北パブは若手がいきいきしている事務所です。「ちょっと聞きたい」を気軽に言える雰囲気があって、それが成長につながっていきます。同期がいることも、すごく大きな支えになります。私自身、入所当初から何度も同期や先輩に助けてもらいました。
クラシック音楽を聴くのが趣味なので、今年はオーケストラの定期会員になって、1〜2か月に1回のペースでコンサートに行っています。リフレッシュになりますね。中高生の頃はクラリネットを吹いていたりもしました。いまはもうちゃんと音を出せるか怪しいですけど(笑)。
クラシック音楽は、本当に多様で奥深いんです。同じ曲でも演奏する人によって解釈や演奏のスタイルもまったく違って、まさに「多様性」にあふれています。生の演奏で音の振動を身体で感じたり、響きに包まれたりするのも大きな魅力ですね。
最近は北パブの若手と一緒に演奏会に行ったりもしました。敷居が高いと感じてしまう人が多いと思いますが、弁護士への法律相談と同様、気軽に行っていただければと思いますね(笑)。
