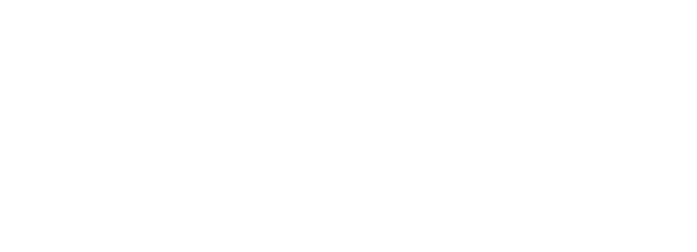
お電話・メールでの
お問い合わせはこちらから
暴行被疑事件で、勾留決定に対する準抗告が認容され、被疑者が釈放される成果を獲得しました。
(弁護士:平岡百合)
2022年5月27日 2:56 PM カテゴリー: 事例報告
金融商品取引法違反被告事件で、保釈請求が認容され、
保釈決定に対する検察官の準抗告申立てが棄却される成果を獲得しました。
(弁護士:酒田芳人、弁護士:平岡百合)
2022年5月27日 2:55 PM カテゴリー: 事例報告
弁護士が入所いたしましたのでお知らせいたします。
森本 真唯 弁護士(74期)
安藤 光里 弁護士(74期)
2022年5月13日 12:42 PM カテゴリー: 弁護士入退所のお知らせ
桑原慶弁護士、上神桂弁護士が4月末で退所いたしましたので、お知らせします。
桑原弁護士は吉田総合法律事務所へ移籍しました。
上神弁護士は親和法律事務所へ移籍しました。
2022年5月13日 12:40 PM カテゴリー: 弁護士入退所のお知らせ

突然、自分の財産が違法なものとして所持を禁止されたら、非常に困った事態に陥るでしょう。
急いでその財産を処分しなければなりません。
日常つかっていたものならば、代わりのものを探す必要もあります。
このたび、厚労省は新たに6物質を指定薬物に指定しました。
令和4年3月7日省令(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212475_00028.html
新たに指定されたうちには、
「HHC」
と呼ばれる物質も含まれています。
このHHCは、“合法大麻”と表現されるほど、大麻の違法成分であるTHCと似た薬効があると言われています。
大麻成分のTHCが日本国内において違法であることに争いはありません。しかし、海外における大麻合法化などの潮流もあり、国内にも大麻の合法化を求める声もあります(医療用に用途を限定するなどいろいろな主張があります)。
そして、大麻の合法化を求めている人たちの間では、HHCが大麻に代替する合法的なものとして流通していました。
僕は、結果的にHHCを規制することに異論はありません。しかし、本件の手続きのあり方については疑問が残ります。
まず、指定薬物は、「厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。(医薬品法2条15項)」とされています。
厚労大臣が指定しますが、
①薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて
②指定する省令を公布して
③施行される
という流れです。
本件で僕が問題だと思うのは、本件の①から③までの時間的な流れのあまりの速さです。
本年の
3/4
薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて①
3/7
省令が公布されて②
3/17
施行されました③
わずか2週間という短期間で、意見聴取・公布・施行されています。
先ほども述べた通りHHC規制に異論はありません。
ですが、それまで合法ということで購入してしまったユーザーなどの財産をいきなり違法なものにしてしまうのに、2週間というのはあまりに短すぎないでしょうか?
それならばどのくらいの期間があればよいのか、という具体的な対案はありませんが、少なくとも2週間は明らかに短すぎます。
たとえそれが危険性のあるドラッグだとしても、国民の財産を制約するおそれがある手続きなのですから、もう少し期間にゆとりをもった手続きをとるべきではなかったでしょうか。
以上
2022年4月5日 2:52 PM カテゴリー: コラム
徳永裕文弁護士、戸塚史也弁護士が3月末で退所いたしましたので、お知らせします。
徳永弁護士、戸塚弁護士はKollectアーツ法律事務所へ移籍しました。
2022年4月5日 2:41 PM カテゴリー: 弁護士入退所のお知らせ