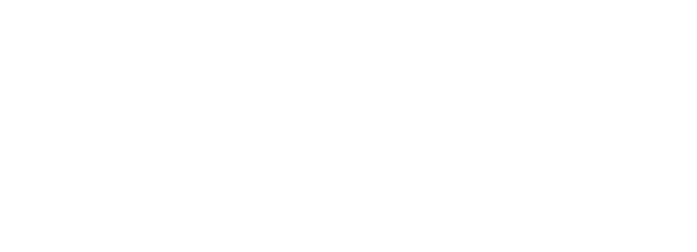
お電話・メールでの
お問い合わせはこちらから
下記の日程で事務所説明会を開催いたします。
参加を希望される方はメールでの事前予約をお願いいたします。
各説明会後には所内にて懇親会も予定しておりますので、参加希望の方は併せて事前予約をお願いいたします。
【開催日】
①2018年 9月27日(木)18時00分〜
②2018年10月24日(水)18時00分〜
【開催場所】
当事務所
【定員】
各30名程度
※②10月24日は、事務所説明会後の18時30分より、刑事実務検討会も予定しております。当事務所の雰囲気を感じていただける機会となりますので、こちらもぜひ奮ってご参加ください。懇親会はその後になります。
なお、事務所説明会はいずれも同じ内容です。
連絡先アドレス info@kp-law.jp
※迷惑メール防止のために@を大文字にしています。お手数ですが、送信の際は小文字に変換の上、お送りください。
2018年8月28日 11:28 AM カテゴリー: 採用情報
2018年9月・10月の法律相談の日程は次のとおりです。
土曜・夜間法律相談も行いますので、ぜひご利用ください。
いずれも電話での事前予約をお願いします。
毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~ ※夜間法律相談
毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週金曜日 (1)13:00~ (2)13:45~
(但し、祝日は除く。)
毎週土曜日 (1)14:00~ (2)14:45~ (3)15:30~ (4)16:15~
※突然逮捕された場合の刑事事件など、緊急の場合には、上記以外の時間で対応できる場合もございますので、お問い合わせください。(ただし、所属弁護士のスケジュールが全てうまっている場合など、お受けできないこともございますので、あらかじめご了承ください。)
【ご予約・お問い合わせ】
03-5284-2101(平日午前9時30分~午後4時30分)
080-9504-1902(土曜日午後1時~午後4時30分)
※携帯電話は、土曜日午後1時~午後4時30分のみの受付になりますのでご注意ください。
※その他、法律相談・事件のご依頼についての詳細は、「初めてご相談される方へ」をご覧下さい。
2018年8月17日 3:51 PM カテゴリー: 法律相談のご案内
最近、架空請求ハガキによる詐欺被害がニュースとなっています。
法務省:はがき、メールなどにより不特定多数の人に対し、身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています。
国民生活センター:「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください!
ITmedia NEWS:「架空請求ハガキ」に注意 法務省かたり「訴訟で財産差し押さえ」 数百万円詐取された被害者も
現在ネットなどで注意喚起がされていますが、こういったネットの注意喚起だけでは被害は大きく減らないだろうと思います。というのも、そもそもハガキを受け取った人が「架空請求かどうか正確に判断できない」からです。
最近は具体的に組織名等をあげて注意喚起がされていますが、それではいたちごっこで根本的な防止策にはなりません。オレオレ詐欺が電話内容を変えていったように、メール詐欺も組織名や請求方法を変えるなどして今後どんどん被害を拡大させていくだろうと思います。
(実際調べてみたところ,「民事訴訟管理センター」とは違う組織名で既に手紙は送られているようです。)
また、「ひょっとしたら、本当に自分が忘れていて支払わないといけないお金かもしれない」という思いが公的機関への相談を躊躇させているのだろうと思います。
そしてメールを見れば、無視をするには不安な額が請求されているので、とりあえず確認と事情を伝えようと、思わず詐欺グループへ連絡を取ってしまうのではないでしょうか。
詐欺グループに素人が連絡をとるのはとても危険です。当然、詐欺グループは架空請求と知ってあえて請求していますから、問い合わせがあれば説得し(請求満額ではないにしても)お金を支払わせるためのマニュアルが準備されているはずだからです。
ただ一方で、この不安な気持ちはある意味で正しいです。あまりネット検索では出てこないのですが、実は法律上、本当に裁判を起こされて何もしないと、「本当は架空請求なのに、支払わないといけなくなってしまう」危険性があります。あるいは、実は架空請求ではないのに誤解をして放置をすれば、裁判で負けてしまい、それこそ執行されてしまう可能性もあります。
こういった事態を避けるために誰に相談すべきでしょうか。架空請求かどうかを正確に判断ができ、裁判を起こされるリスクを判断でき、依頼者に代わって交渉をできるのは弁護士しかいません。
弁護士への相談というとかなりお金がかかるのでは、と思う方もいらっしゃると思いますが、例えば当所の相談料は30分5400円(税込)です。通常30分あれば十分、架空請求かの判断と、今後の対応についてかなり具体的なアドバイスができます。もちろん、架空請求でない通常の請求だとしても、そのまま任意整理として受任することもできます。
詐欺グループはプロ集団ですから、その対応についてもやはり交渉のプロである弁護士にお任せください。もし不安になるハガキが届いたらまずはお気軽に当所までご連絡下さい。電話予約,メール予約どちらも可能です。詳しくはこちらの予約ページをご参照ください。
弁護士 岡田 常志
2018年7月11日 2:11 PM カテゴリー: コラム