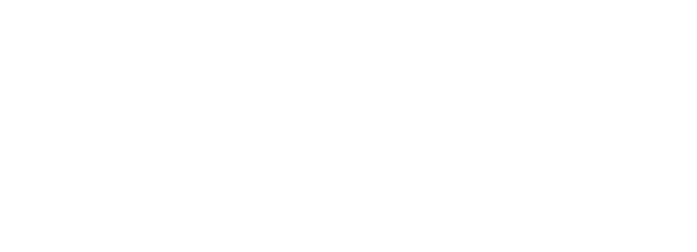
お電話・メールでの
お問い合わせはこちらから
殺人未遂被疑事件(殺意否認)において、暴行罪での罰金10万円という処分にとどめる成果を得ました。(担当弁護士:押田朋大、馬淵未来)
2020年3月2日 9:05 AM カテゴリー: 事例報告
みなさん、こんにちは。
弁護士の寺林智栄(てらばやしともえ)と申します。
現在弁護士13年目です。
北千住パブリック法律事務所は、元々刑事事件専門の公設事務所として開設され、現在もその色合いを濃く残しております。弁護士コラムを見ても、硬派な刑事弁護人的な投稿が多いようです。
そんな中、私は、持ち事件の中で、離婚をはじめとする家事事件の割合が非常に多く、「北パブ家事班」を自称しております。
そんな私ですので(?)、今日は、刑事事件から離れて、弁護士の仕事道具、とりわけ私の仕事道具についてお話ししたいと思います。
当事務所の弁護士に限らず、弁護士の多くは常に多数の案件を抱えており、追われるように仕事をしております。
仕事を要領よくさばいていくためには、効率化できるところはできるだけ効率化し、すぐに対応できる簡単なものはなるべく早めに対処し、「ためない」ことが大切です。
では、そのために、どんな仕事道具が必要なのでしょうか?
みなさん頭に思い浮かべるのは、ノートパソコンではないでしょうか。
外出先でも仕事ができるようにするために、軽量のノートパソコンを常に持ち歩き、ちょっとした暇を見つければ、ぱちぱちキーをたたく。そんなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
実際、当事務所の弁護士の多くは、常にノートパソコンを持ち歩き、暇があればそれを開いて仕事をしております。
私は、実は、パソコンは外出先での待ち時間が長いときしか持ち歩きません。
元々書面は腰を据えてじっくり書きたい方なので、外出先では落ち着かないのです。
外出先で書面仕事を難なくこなせる弁護士は、すごいなあと感じますが、自分はとてもまねできません。
その代わりといってはなんですが、私は、仕事道具として、スマホ・ガラケー・スマホに入っているスキャナアプリの3つを重視しています。
これらは、「たまりがちな雑事をためないようにするため」に必要不可欠なアイテムです。
多くの案件を抱えると、電話やメールでの連絡や問い合わせも多くなります。
外出先だから、事務所に帰ってからお返事しようと思うと、遅くなってしまうことも少なくありません。お返事をするのが遅れると、信用を落としてしまうかもしれません。また、お返事を返すのが、だんだん億劫になってきます。
ですので、外出先・移動中に、電話できるところにはしてしまう、メールの場合には返信してしまうことが重要になると考えています。
なので、私は、メールチェックがいつでもできるようにスマホを常に持ち歩き、仕事用の携帯電話を手元に置いているのです。
また、スキャナアプリは、複数の弁護士で1つの事件、特に刑事事件を担当しているときに役立ちます。
ひとりで被疑者被告人と接見した際にとったメモを、弁護人間で共有するときに、スキャナアプリがあれば、すぐにPDFのデータにすることができ、メールで送ることができます。
もちろん、接見をしながらパソコンで詳細なメモを取ることができればそれが一番いいのでしょうが、残念ながら私はそういう作業は苦手で、メモは手書き派です。
そして、手書きのメモをいちいちパソコンで打ち直す時間は、同じ作業を2度やることになるので、非常にもったいないものです。
時間がなくて打ち直しするのが遅くなると情報共有も遅れてしまいます。
ですから、できるだけ詳細なメモを接見時にリアルタイムで取って、それをアプリでスキャンし、メールで一緒に事件をやっている弁護士に送ってしまうのです。
私が北千住パブリック法律事務所に入所してから1年3か月が経ち、受け持つ案件もかなり多くなってきました。
先に書いたような道具を用いて自分なりに工夫をしていることによって、今のところ、たまりがちな連絡報告をためないで済んでいます。
おかげで事務所で来客がないときには、腰を据えて書面を書く仕事に多くの時間を割くことができているように思います。
今後も持ち事件数は増えていくでしょうから、今お話ししたような効率化は、ますます大切になってくることでしょう。
そのために使い勝手の良い仕事道具があるのであれば、この先も、柔軟に取り入れていきたいと思っています。
2020年2月28日 3:56 PM カテゴリー: コラム
勾留理由開示というものがある。被疑者は、逮捕されると、通常、その後最大20日間、警察署で身柄を拘束される。この最大20日間の身体拘束が勾留である。勾留は、検察官の請求により、裁判官が決定する。
勾留理由開示とは、裁判官に対して、この勾留を決定した理由を問うことができる手続きである。
被疑者を勾留するのは、主に、被疑者が証拠を隠滅したり、逃げたりしないようにするためである。検察官が請求すれば、裁判所はほとんど勾留を認めている。
しかし、弁護人として、この人を勾留する必要などないではないかと感じることは多い。隠滅できる証拠もないし、逃げようもない。それなのに20日もいたずらに拘束されてしまう。
そこで、当の裁判官に対して、なぜこの人を勾留しなければならないのか、その理由を問うのが勾留理由開示の手続である。
20日間どこにも行けず、電話もメールもできない。ひどい時には(弁護士以外とは)面会も手紙もダメ。家族と会う事すら許されない。それ自体重大な人権制約である。
正当な理由もなく、このような制約が許されるはずもない。拘束される側からしてみれば、それだけのことをするなら理由を教えろ、というのは至極当然である。
なお、無論こうした人々の中には、無実の罪で拘束されている人たちも含まれる。
勾留の理由の開示がいかに重要なものであるかは、勾留理由開示が憲法に規定されていることからもわかる。
しかし、この勾留理由開示の手続では、(地域によっても異なるようであるが、)度々、勾留を決定した当の裁判官が出てこないことがある。
勾留理由開示は、公開の法廷で行われる。しかし、ここに、無関係の裁判官が現れて、なぜ勾留の理由を答えられるのか、疑問である。
勾留理由開示の法廷で、裁判官にこの疑問をぶつけてみたところ、返ってきた答えは、「裁判所としては、勾留理由を開示する裁判官は、勾留を決定した裁判官でなくてもよいという見解に立っています。」というものであった。(なぜその見解が妥当なのかについての回答は得られなかった。)
そこで、理由開示を担当する裁判官に、理由開示を担当するにあたって、勾留を決定した裁判官に事前に勾留理由を確認したのか、と尋ねたことがある。
複数の裁判官が、これに対して「答える必要がありません。」という趣旨の回答しかしなかった。事前確認をしたかどうかを明らかにできない理由はないであろうから、事前確認すらしていないということなのだろう。
勾留理由開示において、建設的な理由開示がなされることは残念ながら多くないと認識しているが、無関係な裁判官が(事前確認もなく)担当するのであれば、ある意味それも当然といえる。
勾留というのは、それ自体重大な人権制約である。裁判官にとっては、何十件何百件のうちの一件に過ぎないのかもしれないが、拘束される本人にとっては文字どおり人生を左右する。
理由もなく人を拘束することが許されるはずもない。
裁判官にも諸々事情はあろうが、仮にも勾留を正当とするならば、勾留を決定した裁判官自ら理由開示の場に立ち、どのような質問にも可能な限り丁寧に回答し、その勾留に正当な理由があることを示すくらいのことはしてもらいたいと思う。
それすらできないのであれば、そもそも勾留などすべきではないのだろう。
2020年2月26日 10:00 AM カテゴリー: コラム
昨今ニュースにもなっているとおり,新型コロナウイルス等の流行が全国的に問題となっている状況を考慮し,2020年2月28日(金)開催予定の刑事実務検討会を延期させていただきます。
延期後の日程につきましては,追ってホームページにてお知らせいたします。
すでにご応募いただいた方につきましては大変申し訳ございませんが,ご理解のほどお願い申し上げます。
2020年2月26日 9:47 AM カテゴリー: 研究会等のご案内
2020年3月・4月の法律相談の日程は次のとおりです。
土曜・夜間法律相談も行いますので、ぜひご利用ください。
いずれも電話での事前予約をお願いします。
毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~ ※夜間法律相談
毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週金曜日 (1)13:30~ (2)14:15~
(但し、祝日は除く。)
毎週土曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
※突然逮捕された場合の刑事事件など、緊急の場合には、上記以外の時間で対応できる場合もございますので、お問い合わせください。(ただし、所属弁護士のスケジュールが全てうまっている場合など、お受けできないこともございますので、あらかじめご了承ください。)
【ご予約・お問い合わせ】
03-5284-2101(平日午前9時30分~午後4時30分)
※その他、法律相談・事件のご依頼についての詳細は、「初めてご相談される方へ」をご覧下さい。
2020年2月26日 9:35 AM カテゴリー: 法律相談のご案内
当事務所までお越しの際は、北千住駅(JR、東武線、TX)の西口2階デッキからマルイ脇の道をお通りください。
地上1階からの道順よりも、2階デッキからの道順のほうがおすすめです!
事務所HPの「アクセス」ページは、分かりづらいとのご意見がありました。
http://www.kp-law.jp/access/
そこで、
北千住駅から事務所までの道順動画を作成しました笑
千住ミルディスⅡ番館の3階に到着しますので、エレベーターで6階までお越しください。
法律相談のご予約受付ています!
http://www.kp-law.jp
弁護士 諸橋仁智
2020年2月25日 2:41 PM カテゴリー: コラム